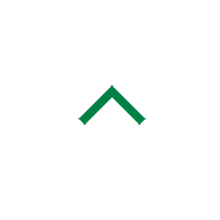2025年6月号: 道路交通法の改正について
-

- L+PRESS 2025年6月 PDFで見る
道路交通法の改正について
1 はじめに
2024年11月に自転車に関する規定としていわゆる「ながらスマホ」や酒気帯び運転等が罰則の対象になる等して、違反行為の罰則の強化が図られました。来年、2026年にもいくつか道路交通法の改正が予定されております。自動車の普及に伴い、多くの方に認知されている道路交通法ですが、今回は、道路交通法の改正について解説を行いたいと思います。
2 道路交通法とは
そもそも道路交通法とは、自動車・自転車・歩行者等の道路を利用するすべての人が守るべきルールを規定したものとなります。そして、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」(道路交通法1条)を目的としております。
3 改正の重要なポイント
今回の改正での1番のポイントとなるのは「生活道路」における制限速度が30kmに引き下げられるという点にあります。かかる規定は、2026年9月1日に施行予定となります。生活道路とは、道路交通法に定義自体がなされているわけではありませんが、国土交通省によると、「買い物や通勤、通学、散歩、立ち話等、地域住民の日常生活で様々な目的で使われる身近な道路」と説明がなされております。そして、今回の改正では、センターラインや中央分離帯がなく、道幅が5.5m未満の狭い道路がこれに該当するとして制限速度の引き下げがなされる予定となります。なお、速度標識がなく、中央線のある幅の広い道路では現行法どおり、制限速度は60kmのままとなります。上記の改正がなされる背景には、交通事故においての死亡事故の約半数が歩行中または自転車乗用中に発生しており、その中でも半数が自宅から近所(約500m以内)での事故であり、生活道路における安全の確保が必要となったという事情があります。また、自動車の速度が約30kmを超えると歩行者との事故の場合、致死率が急激に上昇していることが判明しており、かかる事情から上記改正が行われる予定となります。
4 その他の改正について
上記以外にも、2026年4月には、自転車においても交通違反告知書(いわゆる青切符)の制度が導入される予定となります。これにより、これまで警告や指導等で済ませていた自転車の違反行為に対して、反則金が科せられるようになります。自転車に起因する事故が過去数年で増加傾向にあり、自転車の違反行為について実効性のある取り締まりを行う必要があることから規定されることとなりました。
5 おわりに
今回、ご紹介させていただいたのは一部に過ぎません。改正法が施行されるまでにはまだ期間がございます。企業においては、業務中に自動車や自転車を使用する、通勤時の使用を許可している等であれば、今回は比較的に大きな改正となりますので、予防法務として必要に応じて社内での周知も検討する必要がございます。また、業務内外問わず、交通事故に遭われてしまった場合におかれましてお気軽に当事務所までご相談いただければと思います。

-
【千葉法律事務所】
所属弁護士:大﨑 慎乃祐(おおさき しんのすけ)- プロフィール
- 専修大学法学部法律学科卒業、専修大学法科大学院法務研究科修了。弁護士登録以降、ご依頼者様のトラブル内容に対し、解決するための法的根拠や理由を丁寧に分析し、しっかりした主張を展開して解決に導けるよう、交通事故や一般民事、刑事事件などの分野で活動を行う。趣味はサッカーやジョギング、好きな言葉は「文武両道」。
生き別れとなっていた親の遺留分請求事件
| ご依頼者 | Xさん |
|---|---|
| 相手方 | Yさん |
| 被相続人 | Aさん |
| 被相続人の夫 | Bさん |
| 解決方法 | 交渉 |
| 解決までに要した期間 | 11か月 |
本件の事実関係
Xさんは、Aさんの子でした。しかし、Aさんは、Xさんが3歳の頃、Xさんを養子に出し、以降、Xさんとの交流はありませんでした。
Aさんは、他県でBさんと結婚し、Bさんと生活をしていました。
Aさんは、BさんとBさんの兄弟の子であるYさんに相続させる旨の遺言を遺してなくなりました。Bさんは、Aさんより先に亡くなっておりましたので、遺言書の記載に従い、Yさんが全ての遺産を相続することとなりました。
その後、Aさんの遺言執行者となった司法書士から、Xさんに遺留分がある旨連絡がありました。Xさんは、全く交流のなかった親の相続であること、遺贈を受けたYさんとも全く面識がなかったことから、遺留分を請求するかどうか、相当悩まれていました。最終的には、司法書士とのやり取りから思うところがあり、遺留分請求をすることとし、当事務所にご相談に来られました。
解決までの流れ
Xさんは、Aさんの子ですので、遺留分は2分の1となります。このため、遺産全体の半分を請求する権利がありました。
本件では、司法書士から遺産目録が開示されていました。そして、司法書士がXさんに遺留分がある旨教えてくれていたので、早期解決が可能と思われた事案でした。しかし、Aさんの遺産には、Bさんの遺産が含まれており、相続人間で係争中でした。当該相続分について遺留分の基礎に含まれることを司法書士に理解してもらうことができなかったため、司法書士にYさんを説得してもらうことは早々に諦め、司法書士を関与させることなく、Yさんとのみ交渉を進めることとしました。
私の方で、含まれていなかった遺産加え、遺産の評価をやり直し、Yさんと交渉を開始しました。Aさんの遺産には、再建築不可能な土地建物が残されていたため、先方も処分に困っており、不動産の引取りを求められることもありました。当該不動産は、依頼者が軽々にいけるような距離にはなく、既にYさんの名義となっていたため、結局は金銭で解決することとなりました。
Yさんからも介護等による寄与分の主張があり、かなりの譲歩を迫られましたが、諸々反論に成功し、ほとんど遺留分満額の支払いを受ける形で解決することができました。

-
【千葉法律事務所】
所属弁護士:今井 浩統(いまい ひろのり)- プロフィール
- 東北大学法学部卒業、早稲田大学法務研究科修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、債務整理、過払い金回収、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に、多くの方の法律トラブルをしっかり手助けできるよう活動を行う。趣味はソフトテニス、ゴルフ、アコースティックギター、ドライブ、好きな言葉は「どんなことでも楽しまなくては損」。