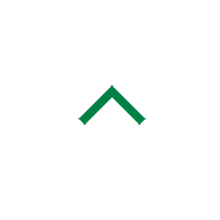2025年7月号: 第三者からの預貯金情報取得手続について
-

- L+PRESS 2025年7月 PDFで見る
第三者からの預貯金情報取得手続について
1 第三者からの情報取得手続とは
第三者からの情報取得手続とは、令和元年の民事執行法改正で新たに設けられた制度です。一定の要件を満たす際に裁判所に申立てをすると、裁判所が情報提供命令に基づいて各第三者機関に対し情報提供を要請し、当該第三者から相手方の財産に関する情報提供を得ることができるという手続です。
情報取得手続の対象には、不動産、勤務先(給与)、預貯金がありますが、以下に述べる通り預貯金の情報取得手続がもっとも使い勝手がよいです。
2 預貯金情報取得手続のメリット
まず、勤務先の情報取得手続を行うためには、請求する権利が養育費、婚姻費用などや生命身体の損害賠償請求権に限られますが、預貯金(不動産も)の情報取得手続の場合はそうした限定がありません。
また、不動産や勤務先の情報取得手続では、事前に裁判所に財産開示手続(相手方を裁判所に呼び出し、所持している財産の内容を問いただす手続)を申し立てて手続が終わっている必要がありますが、預貯金の情報取得手続ではその必要もありません。
加えて、預貯金の情報取得手続においては、不動産や勤務先の場合と異なり、情報提供命令が出され各金融機関から情報提供が始まっても、情報取得手続が始まったことはすぐには相手方に知らされません。相手方に情報取得手続が行われたことが知らされるのは、最後の情報提供があってからおおむね1カ月後となっています。このため、複数の金融機関に情報取得手続を行う場合、最後の回答があってから1カ月程度の時間の猶予があり、それまでにめぼしい金額のある口座を差し押さえればよいのです。
以上から、預貯金の情報取得手続はもっとも密行性にすぐれており、金銭執行を行うにあたってはまず預貯金の情報取得手続を検討すべきということになります。
3 預貯金情報取得手続の留意点
対象とする金融機関の選定については、メガバンクとゆうちょ銀行が第一選択、あとは相手方の生活圏ないし事業場所に応じた地銀・信用金庫などを候補とします。相手方が個人の場合、メジャーなネット銀行を対象にすることも検討したほうがよいでしょう。相手方が法人なら、ウェブサイトやこれまでの取引関係書類で取引先銀行を調べる方法もあります。
申立てにおいては、口座が相手方の旧住所や旧氏名(旧名称)で作られていることもあるので、相手方の生年月日や会社設立日、氏名や会社名の読み仮名、旧住所、旧姓(旧会社名)などの情報を、戸籍の附票や登記事項証明書などを用いてできるだけ広く特定する必要があります。
情報提供は五月雨式に来るため、ある程度まとまった金額の口座が見つかった場合は、他の情報提供を待たずにすぐに差し押さえたほうがよいでしょう。
情報取得手続が相手方に知られると相手方も財産隠しに動く可能性が高くなることから、預貯金情報取得手続は事実上の一発勝負と考え、抜かりなく準備を進める必要があります。

-
【上野法律事務所】
所属弁護士:若松 俊樹(わかまつ としき)- プロフィール
- 東京大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了後、弁護士登録以降東京で6年、茨城県水戸市で6年半強ほど一般民事や企業法務などの分野で執務。現在は上野事務所で、交通事故、労働事件などを中心に活動を行う。趣味は読書や音楽鑑賞、好きな言葉は「鬼手仏心」、「神は細部に宿る」。
交通事故解決事例
Aさん(80代女性)が自転車に乗って信号のある交差点の横断歩道上を青信号で直進していたところ、右折してきた相手方自動車に右方から衝突されました。Aさんは、衝突により、腰椎骨折等の傷害を負い、後遺障害等級10級が認定され、その後、保険会社から示談の提案がありました。
被害者が高齢の場合、後遺障害逸失利益は認められますか。
後遺障害が残ったことにより労働能力を喪失し、将来の収入の減少が見込まれる場合には、後遺障害逸失利益(将来の収入の減少分を補償するもの)が損害として認められます。
高齢で仕事をしていない場合、原則として、将来の収入の減少が想定できないため、後遺障害逸失利益は認められません。
しかし、被害者が、同居の家族のために家事労働に従事している家事労働者である場合は、後遺障害逸失利益が認められます。
家事労働者は、現実の収入があるわけではありませんが、交通事故の賠償の場面では、家事労働について、女性労働者の平均賃金に相当する財産上の収益をあげるものと推定されます。後遺障害により、従来通りの家事労働ができないのであれば、その点を後遺障害逸失利益に換算することとなります。
本件でも、被害者は、同居の家族のために家事労働をされていた方でしたので、家事労働者としての後遺障害逸失利益を請求した結果、保険会社は、後遺障害逸失利益の支払に応じました。
弁護士に頼んだら、保険会社の賠償提案額から必ず増額してもらえますか。
弁護士に頼んだら必ず保険会社の賠償提案額から必ず増額できるということはありません。しかし、弁護士に頼まず、個人で保険会社と交渉する場合、保険会社は、最低限度の金額での示談を持ちかけてくることが多いです。また、保険会社に増額を求めても、弁護士による交渉でないと、保険会社がまともに応じてくれないことがよくあります。
弁護士による交渉の場合、法的に認められる範囲で最大限の損害賠償金額を見極めて交渉すること、示談にならなければ訴訟提起の手段がすぐに取れること等から、保険会社も当初の金額からの増額に応じる傾向があります。
Aさんのケースでは、弁護士が活動した結果、傷害慰謝料や後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等の大幅な増額に成功し、最終的に、保険会社の当初提案額から約480万円の増額をすることができました。
保険会社からの示談提案がされたら、示談書にサインする前に、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

-
【市川法律事務所】
所属弁護士:村田 羊成(むらた よしなり)- プロフィール
- 中央大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行い、ご依頼者様の人生やビジネスに立ちはだかる困難を取り除き、解決するために奔走している。好きな言葉は「学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること」