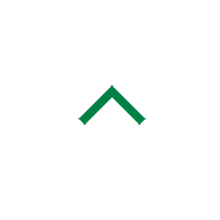2025年9月号: 解雇・雇止め・内定取消しについて
-
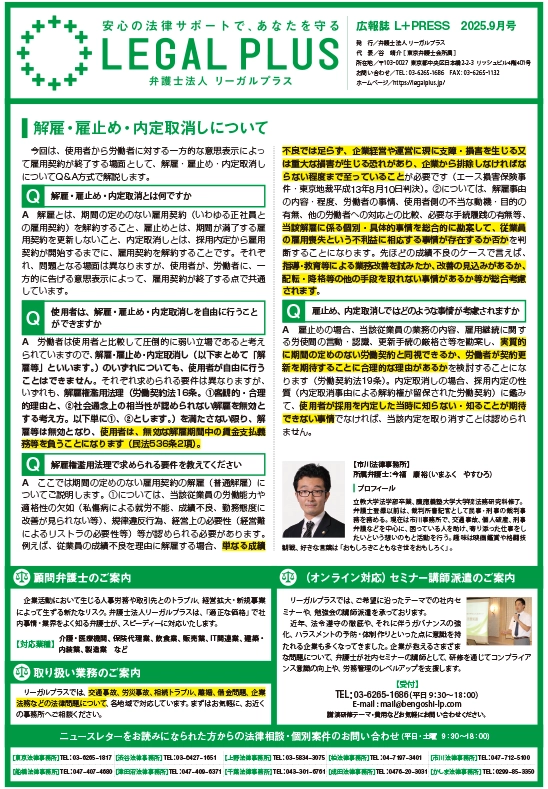
- L+PRESS 2025年9月 PDFで見る
解雇・雇止め・内定取消しについて
今回は、使用者から労働者に対する一方的な意思表示によって雇用契約が終了する場面として、解雇・雇止め・内定取消しについてQ&A方式で解説します。
解雇・雇止め・内定取消とは何ですか
A 解雇とは、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員との雇用契約)を解約すること、雇止めとは、期間が満了する雇用契約を更新しないこと、内定取消しとは、採用内定から雇用契約が開始するまでに、雇用契約を解約することです。それぞれ、問題となる場面は異なりますが、使用者が、労働者に、一方的に告げる意思表示によって、雇用契約が終了する点で共通しています。
使用者は、解雇・雇止め・内定取消しを自由に行うことができますか
A 労働者は使用者と比較して圧倒的に弱い立場であると考えられていますので、解雇・雇止め・内定取消し(以下まとめて「解雇等」といいます。)のいずれについても、使用者が自由に行うことはできません。それぞれ求められる要件は異なりますが、いずれも、解雇権濫用法理(労働契約法16条。 ①客観的・合理的理由と、②社会通念上の相当性が認められない解雇を無効とする考え方。以下単に①、②とします。)を満たさない限り、解雇等は無効となり、使用者は、無効な解雇期間中の賃金支払義務等を負うことになります(民法536条2項)。
解雇権濫用法理で求められる要件を教えてください
A ここでは期間の定めのない雇用契約の解雇(普通解雇)についてご説明します。①については、当該従業員の労働能力や適格性の欠如(私傷病による就労不能、成績不良、勤務態度に改善が見られない等)、規律違反行為、経営上の必要性(経営難によるリストラの必要性等)等が認められる必要があります。例えば、従業員の成績不良を理由に解雇する場合、単なる成績不良では足らず、企業経営や運営に現に支障・損害を生じる又は重大な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度まで至っていることが必要です(エース損害保険事件・東京地裁平成13年8月10日判決)。②については、解雇事由の内容・程度、労働者の事情、使用者側の不当な動機・目的の有無、他の労働者への対応との比較、必要な手続履践の有無等、当該解雇に係る個別・具体的事情を総合的に勘案して、従業員の雇用喪失という不利益に相応する事情が存在するか否かを判断することになります。先ほどの成績不良のケースで言えば、指導・教育等による業務改善を試みたか、改善の見込みがあるか、配転・降格等の他の手段を取れない事情があるか等が総合考慮されます。
雇止め、内定取消しではどのような事情が考慮されますか
A 雇止めの場合、当該従業員の業務の内容、雇用継続に関する労使間の言動・認識、更新手続の厳格さ等を勘案し、実質的に期間の定めのない労働契約と同視できるか、労働者が契約更新を期待することに合理的な理由があるかを検討することになります(労働契約法19条)。内定取消しの場合、採用内定の性質(内定取消事由による解約権が留保された労働契約)に鑑みて、使用者が採用を内定した当時に知らない・知ることが期待できない事情でなければ、当該内定を取り消すことは認められません。

-
【市川法律事務所】
所属弁護士:今福 康裕(いまふく やすひろ)- プロフィール
- 立教大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。弁護士登録以前は、裁判所書記官として民事・刑事の裁判事務を務める。現在は市川事務所で、交通事故、個人破産、刑事弁護などを中心に、困っている人を助け、寄り添った仕事をしたいという想いのもと活動を行う。趣味は映画鑑賞や格闘技観戦、好きな言葉は「おもしろきこともなき世をおもしろく」。
交通事故解決事例
1 事案の概要
Xさんは、自動車を運転中、信号待ちで停車していたところ後続車に追突されました。むち打ちで6カ月弱通院し、2カ月後、保険会社から示談書等が届きました。そこで、弁護士費用特約を使用して増額交渉できないかとご相談のお電話をいただき、増額可能性が高かったため、ご依頼をいただきました。
2 保険会社の提案内容と交渉方針
問題点は、①通院慰謝料が低額、②休業損害が、週40時間以上勤務を理由に主婦としての損害を認めず、給与所得者としての証明書から算出される金額に止まること、の2つでした。
Xさんは、時間のかかる裁判は望まず、適正な範囲内の早期解決をご希望でしたので、①の慰謝料は、支払いが渋いことで有名な担当者特性も考慮して裁判基準の85%を目標としつつ、②の主婦休損を認めさせて総額を伸ばすことにしました。
3 通院慰謝料の交渉結果
案の定、裁判基準90%での当方案に対して、担当者は80%との対案を書面で送りつけてきて、後述の主婦休損と引き換えに85%で落ち着きました。
但し、通院期間よりも回数の3倍の方が少ないケースのため、一部の強硬な会社・担当者だと低額な回数ベースでしか応じないのですが、本件担当者は裁判基準の原則である期間ベースは認める常識的な対応で、金額的に約9割の増額となりました。
4 兼業主婦の休業損害と交渉結果
兼業主婦の休業損害算定の基礎となる収入について、裁判基準は「現実の収入金額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方」としており、自賠責保険の支払基準とは異なり、勤務時間は基本的に無関係です。
但し、日額が(自賠責基準6,100円に対し)1万円を超える反面、休業日数の認定は相応に厳しくなります。休業日数・総額をある程度抑えるさじ加減も、保険会社側の弁護士介入や訴訟を避けて適切な早期解決を目指す場合には重要です。
本件では、休業損害証明書ベースの提案に対して8割の増額となりました。
5 ポイントは弁護士費用特約とカバー範囲
総額で約50万円の増額となりました。弁護士費用のご負担はなく、増加額が全てお手元に残るという意味で、やはり弁護士費用特約は必須だと思います。
近時は、弁護士費用特約が自動車事故限定型しかない保険会社もあり、自転車にぶつけられ大けがをしたのに特約を使えないというご相談も増えています。やはり日常生活事故を含む弁護士費用特約を選びたいものです。
また、代理店経由で自動車保険を契約されている方で、弁護士費用特約を付けたはず(代理店に問い合わせて大丈夫と回答された)なのに、いざ事故に遭ったら実は代理店のミスで付いていなかったというご相談も散見されます。やはり保険証券で特約の〇×を確認することも必要だと思います。

-
【上野法律事務所】
所属弁護士:上田 和裕(うえだ かずひろ)- プロフィール
- 早稲田大学政治経済学部卒業。大学卒業後は電機メーカーに就職し、より専門性が高い仕事をしたい、職人としての誇りが持てるようになりたいと思い、転職を経て法曹を目指す。現在は上野法律事務所に所属し、依頼者の利益を最優先に思考し行動することを心がけている。好きな言葉は「人事を尽くして天命を待つ」。