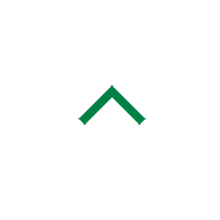2025年10月号: 民法改正で変わる養育費制度:企業が知っておくべき「法定養育費」と「先取特権」
-
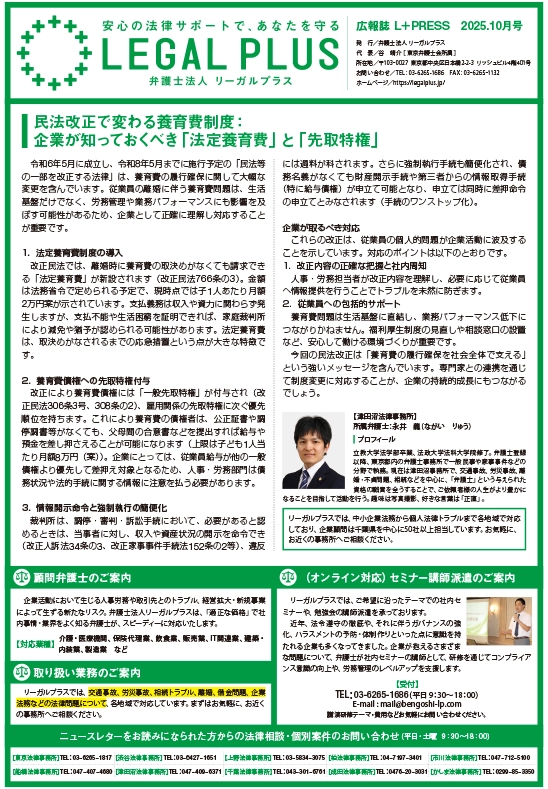
- L+PRESS 2025年10月 PDFで見る
民法改正で変わる養育費制度:
企業が知っておくべき「法定養育費」と「先取特権」
令和6年5月に成立し、令和8年5月までに施行予定の「民法等の一部を改正する法律」は、養育費の履行確保に関して大幅な変更を含んでいます。従業員の離婚に伴う養育費問題は、生活基盤だけでなく、労務管理や業務パフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があるため、企業として正確に理解し対応することが重要です。
1.法定養育費制度の導入
改正民法では、離婚時に養育費の取決めがなくても請求できる「法定養育費」が新設されます(改正民法766条の3)。金額は法務省令で定められる予定で、現時点では子1人あたり月額2万円案が示されています。支払義務は収入や資力に関わらず発生しますが、支払不能や生活困窮を証明できれば、家庭裁判所により減免や猶予が認められる可能性があります。法定養育費は、取決めがなされるまでの応急措置という点が大きな特徴です。
2.養育費債権への先取特権付与
改正により養育費債権には「一般先取特権」が付与され(改正民法306条3号、308条の2)、雇用関係の先取特権に次ぐ優先順位を持ちます。これにより養育費の債権者は、公正証書や調停調書等がなくても、父母間の合意書などを提出すれば給与や預金を差し押さえることが可能になります(上限は子ども1人当たり月額8万円(案))。企業にとっては、従業員給与が他の一般債権より優先して差押え対象となるため、人事・労務部門は債務状況や法的手続に関する情報に注意を払う必要があります。
3.情報開示命令と強制執行の簡便化
裁判所は、調停・審判・訴訟手続において、必要があると認めるときは、当事者に対し、収入や資産状況の開示を命令でき(改正人訴法34条の3、改正家事事件手続法152条の2等)、違反には過料が科されます。さらに強制執行手続も簡便化され、債務名義がなくても財産開示手続や第三者からの情報取得手続(特に給与債権)が申立て可能となり、申立ては同時に差押命令の申立てとみなされます(手続のワンストップ化)。
企業が取るべき対応
これらの改正は、従業員の個人的問題が企業活動に波及することを示しています。対応のポイントは以下のとおりです。
- 改正内容の正確な把握と社内周知
人事・労務担当者が改正内容を理解し、必要に応じて従業員へ情報提供を行うことでトラブルを未然に防ぎます。 - 従業員への包括的サポート
養育費問題は生活基盤に直結し、業務パフォーマンス低下につながりかねません。福利厚生制度の見直しや相談窓口の設置など、安心して働ける環境づくりが重要です。
今回の民法改正は「養育費の履行確保を社会全体で支える」という強いメッセージを含んでいます。専門家との連携を通じて制度変更に対応することが、企業の持続的成長にもつながるでしょう。

-
【津田沼法律事務所】
所属弁護士:永井 龍(ながい りゅう)- プロフィール
- 立教大学法学部卒業、法政大学法科大学院修了。弁護士登録以降、東京都内の弁護士事務所で一般民事や家事事件などの分野で執務。現在は津田沼事務所で、交通事故、労災事故、離婚・不貞問題、相続などを中心に、「弁護士」という与えられた資格の職責を全うすることで、ご依頼者様の人生がより豊かになることを目指して活動を行う。趣味は写真撮影、好きな言葉は「正直」。
交通事故解決事例
1 事案の概要と交渉経緯
Xさんは、赤信号で停止中に相手方車両から追突され、むちうちなどの怪我を負いました。Xさんは、男性でしたが、事故当時はいわゆる専業主夫であり、日常的に家事労働を行う一方、金銭的な収入は得ていませんでした。Xさんは、事故によって約6カ月の通院を余儀なくされ、家事労働にも支障が生じていましたが、保険会社はXさんを「無職」として扱い、休業損害の支払に一切応じませんでした。そのまま交渉は決裂し、弁護士が交通事故紛争処理センターへ和解あっせんを申し立てる運びとなりました。
2 専業主夫の休業損害
今日の多様化社会においては、専業主夫は決して珍しい存在ではなくなりました。もっとも、「センギョウシュフ」といえば、女性であることの方がまだまだ多いのも事実です。そのためか、あくまで肌感覚にとどまりますが、男性が家事従事者として休業損害を請求する場合、保険会社がこれを認容するハードルが女性の場合よりも高く設けられているような印象を受けます。本件でも、相手方保険会社は、交渉段階でXさんの配偶者の収入がわかる資料の提出を求めてきました。Xさんが本当に専業主夫なのであれば、配偶者が大黒柱であるはずであり、配偶者に相応の収入があってしかるべきという判断から出てきた主張と思われますが、家事従事者として休業損害を請求する際にここまで提出を求められることは通常ありません。
なお、本件では、Xさんが専業主夫でいる期間はもともと限定的にする予定であり、事故当時は近く再就職をして仕事に復帰する予定だったという事情があり、配偶者の収入は長期的に家計を支えられるほどの金額ではありませんでした。このため、上記資料の提出にかかわらず、相手方保険会社はXさんを家事従事者と認定しませんでした。
3 紛争処理センターの利用
交通事故を含む損害賠償トラブルにおいて、交渉が困難となった場合、通常は訴訟の提起という選択肢が考えられます。しかし、交通事故の場合は、交通事故紛争処理センターという機関に和解あっせんを申し立てて解決を図る方法も考えられます。センターから嘱託を受けた第三者の弁護士が間を取り持ち、当事者双方の意見を踏まえたうえで和解案を作成するというものです。
訴訟と比較した場合の最大のメリットとして、比較的短期間で解決に至る可能性が高いことが挙げられます。訴訟では解決まで1年以上かかることも多々ありますが、和解あっせんの場合、3カ月から6カ月程度で解決に至ることが一般的です。本件では、上述の経緯から交渉がまとまらなかった一方、休業損害が唯一の争点であり、スピーディーな解決が図れると考えられたことから、和解あっせんの申立てという方法を選びました。
結果、保険会社からの求めに応じてさらに住民票やXさんの陳述書などを提出することとなりましたが、最終的には申立てから3カ月程度でこちらの請求額がほぼ100%認められることとなりました。

-
【柏法律事務所】
所属弁護士:宇野 浩亮(うの こうすけ)- プロフィール
- 一橋大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。弁護士登録後は柏法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行い、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、信頼される関係をしっかりと構築しながら解決に向けた活動を行う。好きな言葉は「一期一会」。